お子さんの成長には「協働性(きょうどうせい)」というスキルがとても重要となります。
協働性とは、仲間と協力しながら目標を達成する力のこと。
将来の人間関係や社会での生活に大切なスキルですよね。
この記事では、協働性の意味や協調性との違い、そして親ができるサポートについて詳しくお話しします。
また、協働性を高めるための具体的な方法として、オンライン英会話やその他のおすすめ習い事も紹介します。
今回の内容がお子さんの成長を応援するためのヒントとなれば幸いです。
これまで計10社以上のオンライン英会話を見てきた私がおすすめする『QQキッズ(QQEnglish)』の評判についてもぜひチェックしてみてください。
協働性とは?
協働性とは、仲間と協力し合いながら共通の目標を達成する力のことです。
例えば、クラスのプロジェクトやスポーツチームでの活動では、他のメンバーと一緒に力を合わせることが求められます。
協働性を育むことで、コミュニケーション能力や問題解決能力が向上し、将来の人間関係や社会生活での成功につながります。
協働性を理解し、その重要性を知ることは、親としてお子さんの成長をサポートするための大きな手助けとなるはずです。
協働性はこれからの時代には特に必要とされるスキルです!
早いうちから意識して育てていくことが、お子さんの健やかな成長につながるでしょう。
〈学力の三要素〉
— ミヤシロリョウ (@plus5_ryo) December 19, 2024
1.知識・技能
2.思考力・判断力・表現力
3.主体性・多様性・協働性。
すでに大学入試でも「この三要素をバランス良く評価すること」を求められています。
もはや「学力」は数値で語るものではなくなりつつあります。
協調性との違いは?
協調性は、他の人との仲を大切にし、調和を保つ力のことです。
たとえば、友達とケンカせずに仲良く過ごしたり、クラスメイトと仲良く一緒に遊んだりすることが協調性です。
一方で、協働性は、みんなで協力して目標を達成する力のことです。
クラスでプロジェクトをやるときや、スポーツチームで勝利を目指すときなどに必要となります。
- 協調性=仲良くすることを重視
- 協働性=みんなで力を合わせて目標を達成すること
協働性が高いとどうなる?
協働性が高い人は、リーダーシップを発揮しやすくなります。
例えば、クラスのグループプロジェクトなどで自然とリーダー役を引き受け、みんなをまとめて目標を達成することができます。
友達と協力して難しい問題を解決する際にも、その能力が活かされます。
また、コミュニケーション能力が高まり、他の人と上手に話し合ったり意見を交換するのが得意になるでしょう。
そのため、クラスのディスカッションでも活躍する場面が増えます。
さらに人間関係が良くなり、友達や家族との関係も円滑になる可能性が高くなります。
例えば友達とのちょっとしたケンカがあっても、協働性が高い子供はすぐに仲直りできる能力を持っています。
家族との関係でも、お手伝いや家族行事の計画を積極的に行い、家庭内の雰囲気を良くすることが期待できます。
なぜ今「協働性」が求められるのか
いま、社会や学校では協力して物事を進める力、つまり「協働性」がとても大切だと言われています。
では、なぜそれが必要なのか、教育・ビジネス・そして地域社会の視点からその理由を見ていきましょう。
1.教育における協働学習
学校ではただ知識を詰め込むだけでなく、友達と協力して学ぶことがとても大切です。
学生の頃、授業のグループワークや友達と共同で進める取り組みで、新しい発見をした経験はありませんか?
例えば、文化祭の準備や体育祭の競技にみんなで取り組むことで、一緒に楽しみながら新しいことを学ぶ機会があったかもしれません。
このような経験を通じて、友達と協力することの大切さを学ぶことができます。
2.ビジネスの場面でも必要
大人になって働くと、チームで進められる仕事も多くあります。
例えば、大きなイベントの開催では、企画担当・宣伝担当・運営担当などが力を合わせて取り組む必要がありますよね。
SNSの発展で情報を簡単に得られるようになった反面、社会ではコミュニケーション能力がますます重要とされています。
現代では、新しいミッションを成功させるために話し合い、知識やアイデアを共有することが求められます。
SNSだけでは得られない新しい発想や解決策は、人と人が直接コミュニケーションを取ることで生まれることが多いためです。
会社はいろんな人の集まり。
— 山口晋平|人事屋@EMPOWERMENT㈱ (@shimpei_guchi) June 16, 2022
自分で考えて行動すれば揃わないのが当たり前。
ブランドを作るためには主体性よりも協働性が大切。
ルールを明確にしみんなで守る。
画像はそれぞれの部署で作ってもらっていた日報。
ここから形を揃える。 pic.twitter.com/GTHKPsQ1Am
こちらの投稿では、現代の企業において協働性が重要であることを強調しています。
様々な背景やスキルを持つメンバーが集まる会社では、自分一人で行動するだけでは統一感が生まれませんよね。
AI技術の進化により、人を介さずにできる業務が増えていますが、人同士の対話から生まれる新たな価値も大切です。
協働性がこれからの社会で成功するための重要なポイントになると言えそうです。
3.地域や社会活動での重要性
地域や社会活動でも、協働性は欠かせません。
例えば、地域の清掃活動を見てみましょう。
近所の住民たちが協力して道路や公園のゴミを拾い、環境をきれいに保つために一緒に取り組みます。
みんなで協力することで地域全体が一体感を持ち、共通の目標を達成する喜びを感じることができます。
子供が協働性を育むことで得られる7つのメリット
ここでは、子供が協働性を育むことで得られる7つの主なメリットについて紹介します。
メリット①自己肯定感が高まる
子供はチームでの達成感を味わうことで、自分の役割や貢献に対する自信が高まります。
例えば、サッカーの試合でチームメイトと協力してゴールを決めることができた時は、自分がチームにとって重要な存在であることを実感します。
また、学校の文化祭でクラス全員が協力して劇を成功させた場合なども同様です。
このような経験を通じて、子供は「自分の努力がチームに貢献している」と感じ、自信を持つことができます。
メリット②良好な対人関係
協働性を伸ばすためには、協働学習が不可欠です。
協働学習とは、複数の学習者が協力して課題やプロジェクトに取り組み、お互いに学び合う教育の方法です。
≪協働性を高めるために必要な要素≫
- 子供たちには、どんな人とでも協力し、成功するための環境が大切。
- 異なる性格の子供たちと共通の目標に向かって協力する。
- 他者の話に耳を傾け、共感し、他人の意見を尊重することを学ぶ。
このような経験や失敗を繰り返すことで、自然と良好な対人関係が築かれます。
このスキルは、将来の社会生活やチームワークにおいて重要な役割を果たしますよね!
協働性は、子供たちが自信を持って様々な場面で活躍するための基盤とも言えるでしょう。
メリット③ 勉強に対する熱意が高まる
協働性を高めることで、発想力や問題解決能力が鍛えられます。
例えば、小学校の社会科の授業で、クラス全員が協力して地図を作成する場面を考えてみましょう。
子供たちはグループに分かれ、それぞれ異なる地域の情報を調べます。
一つのグループが「山の地形について調べよう」、別のグループは「川や湖について調べよう」とアイデアを出します。
みんなで調べた情報を持ち寄り地図を完成させる過程で、地域の特徴や歴史について学びますよね。
この過程で子供たちは互いの意見を取り入れながら、新しい発見をし、社会科の面白さを実感します。
また、グループ学習が楽しいと感じる子供が増え、学習意欲も自然に高まる効果が期待できます。
協働性を高めるグループでの学習には多くのメリットがあることがわかりますよね。
親としても、子供の勉強に対する熱意が高まることは大きなメリットです!
思考力の発達や会話力の向上などにもつながり、多くの利点が得られます。
メリット④創造力が強化される
他者との対話や意見交換を通して、多様な視点や考え方を取り入れることができます。
例えば、学校での班活動でクラスの壁新聞を作成する場面を考えてみましょう。
班のみんなでテーマやデザインについて話し合います。
一人が「自然について書こう」と提案し、別の子が「写真をたくさん使おう」とアイデアを出し合いながら作業を進めていきます。
こうして子供たちは互いの意見を取り入れながら、新しいアイデアや創造力を引き出していきます。
多くの小学校では、班活動での協力が子供たちにとって重要な学びの場となっています。
「自分の子供は発想力がないかも」と不安に感じるかもしれませんが、協働性を高める学習では発想力が鍛えられ、自分で新しいアイデアを考え出す喜びに気づけるようになっていくでしょう。
メリット⑤問題解決能力の向上
他者と協力しながら課題を解決する経験を積むことで、問題解決能力が向上します。
ここで、私の子供が小学校の班活動で直面した問題や解決までの話を紹介させてください。
私の子供は、学校の庭に新しい花壇を作る活動に取り組んでいました。
最初にどの花を植えるかを話し合う中で、「色がきれいな花を植えよう」「低い花を植えて見やすくしよう」といった意見が出たとのこと。
しかし、実際に作業を進める中で、土が固くて花を植えづらいという問題が発生。
他の子供は「水をまいて土を柔らかくしよう」と提案し、私の子供は「スコップで土を細かくして耕そう」と意見を出し合ったそうです。
このように班活動を通じて協力し、互いの意見を取り入れながら課題を解決する方法を学んだようです。
このような経験を重ねながら、問題解決能力が高められていくのでしょうね。
メリット⑥協力の精神が育まれる
一緒に取り組むことで協力の精神が育まれていきます。
例えば地域のゴミ拾い活動に参加することで、子供たちは地域の美化に貢献する喜びを感じながら、他者と協力することの大切さを学ぶでしょう。
若手の方々はチームワークスキルを磨こう。
— まっちゃん|若手社会人の味方 (@MacchanForYoung) January 7, 2021
メリットは3つ。
❶必要不可欠な人になれる
👉チームを創れる人は希少価値が高い。
❷成果をあげやすくなる
👉みんなとの協働で成果を目指せます。
❸仕事が楽しくなる
👉チームが居心地が良くなる。これ大事。
1年目からやろう。気持ちひとつ。
このポストにあるように、協力の精神やチームワークのスキルは、どの年齢層においてもとても重要ですよね。
早い段階から他者との協力を学ぶことで、将来的に必要不可欠な存在となり、成果を上げやすくなるでしょう。
さらに、仕事や日常生活も楽しくなるのではないでしょうか。
子供たちにとっても、協力の重要性を理解し実践することは、人生の大きな財産になりますよね!
メリット⑦取り組む意欲が増す
自分の意見やアイデアが尊重される環境で活動すると、積極的に参加しようとする意欲が自然と高まります。
学級委員がクラスの意見をまとめる場面を考えると、まとめる側は「みんなの意見を尊重し協力する大切さ」を学び、他の生徒は「自分の意見が大切にされている」と感じるのではないでしょうか。
このような経験を通して、取り組む意欲が自然に高まるでしょう。
子供たちはこんな風に教育したかったけど、結局辞書は埃被っております😭 英語の辞書も使ってるの私だけ💧
— なっつ (@seven_sounds) January 20, 2025
なんでも前向きに取り組む子にものすごく憧れます😅(親目線として…) 勉強意欲としては最高のやり方ですよね🎶
こちらにもあるように「なんでも前向きに取り組む子」には憧れますよね。
取り組む姿勢を持つ子供たちは勉強意欲が自然と高まり、それが結果として将来の成功に繋がっていくのだと思います。
協働性を育てるために親ができるサポートは?
次に、協働性を育むために親ができる具体的なサポートについて、7つご紹介します。
①失敗を見守りながら成功をサポートする
協働性を育むために親ができる具体的な行動は、子供が失敗しても怒らずに見守り、成功するまでサポートすることです。
例えば、子供が料理を手伝ってくれる時など、初めての試みで失敗することはありますよね。
初めて卵焼きを作ってみると、卵がうまく焼けずに焦げてしまった・形が崩れた…など。
そのような場合は怒らずに見守り、次回はどうすれば上手くできるか一緒に考えましょう。
最終的に美味しい卵焼きを作ることで、自信を持つようになるでしょう。
失敗した後、何が間違っていたのかを優しく教えてあげることで、子供はその経験を覚えて学びに活かします。
親が『伝わりやすい・わかりやすい言葉』を使うことで、子供も学校などで分かりやすく話し、相手とのコミュニケーションがスムーズになります。
この点についても、親がしっかりとサポートしていきたい部分ですね。
②家族以外の人と交流を深める
家族以外の人と交流を深めることも、協働性を育むために重要です。
友達や近所の人と一緒に遊ぶことで、子供たちは社会性を学び、協力することの楽しさを実感します。
地域のイベントやお祭りに参加することも、家族以外の人との交流を深める良い機会です。
地域の人々と一緒に活動することで、子供たちは多様な人々と関わり合いながら、協力の大切さを学びます。
このように、家族以外の人と交流を深めることは、子供たちの協働性を育むために大切なサポートの一つです。
③家族全員で役割を決めて取り組む
協働性を育てるために親ができるサポートとして、家族全員で役割を決めて取り組むことも効果的です。
始めは簡単で達成感のある役割が良いでしょう。
例えば、食器の片付けやテーブルの準備・植物の水やりや玄関の靴をきれいに並べるなど。
これにより責任感を養い、達成感を味わうことで、次第にもっと難しい役割にも挑戦する意欲が高まります。
④子供に家庭でのお手伝いを任せる
子供に家庭でのお手伝いを任せることも協働性を育むサポートとなります。
家庭内での小さな手伝いを通じて、子供たちは責任感と協力の精神を身につけます。
我が家では、子供が食事の後片付けを手伝うことにしています。
今では家庭内での協力が日常的になり、協働性が育まれていると感じていますよ。
家族みんなで協力して、料理を作れば、もっと楽しくなるはず。子供にも、簡単な手伝いを頼んでみようかな。
— こころ@ (@koko0wBN4180795) December 8, 2024
⑤地域や学校のボランティア活動に参加する
地域や学校のボランティア活動に参加することも、協働性を育むのに役立ちます。
私の子供は学校の廃品回収に参加した際、他の参加者と協力し一緒に廃品を分別する過程を体験しました。
周囲の大人から「ありがとう」や「頑張っているね」などの声掛けも嬉しかったようで、この活動を通して協力して働くことの楽しさを実感していましたよ。
⑥映画鑑賞で感情表現を学ぶ
感情表現を学ぶために映画鑑賞をすることも効果的です。
例えば家族で感動的な映画を観ると、子供たちはそのシーンに共感し、自分の感情を表現する練習になりますよ。
映画鑑賞後に家族で感想を共有すると、自分の感じたことを言葉にする力も養われます。
「あの場面で主人公が悲しかった理由は何だろう?」などの質問を通じて感情表現の大切さを理解し、協力する意欲が高まるでしょう。
映画を通じて喜怒哀楽を学び、子供たちは他者との共感を深めることができます。
⑦ 読書習慣をつける
読書は子供たちの想像力を広げ、感受性や共感力を育むために非常に効果的です。
我が家では子供に読書の習慣をつけるために、私も読書をしてその姿を子供に見せるようにしていますよ。
物語を通じて、子供たちは登場人物の気持ちや行動を理解し、共感することを学びます。
また感想を話し合うことで子供たちは自分の考えを言葉にする力を養い、読書を通じて得た知識や経験を共有することで、自然に協働性を身につけていきます。
子供の頃から本が好きで、
— ゆう (@hanasora1616) May 15, 2024
あっという間に1冊読んでしまう子だった。
読書感想文も書くのも好きでした🍀
あの頃の、主人公の気持ちをわかりすぎて涙ポロポロこぼしてた感受性が
今の楽器に役立ってるかも😊
こちらの方は、読書を通じて身につけた感受性や表現力が、現在にも大きく役立っているようですね。
子供たちにも同様に、読書を通じて豊かな感受性と共感力を育んでほしいですね。
協働性を育むために、親ができる具体的なサポートを紹介しました。
地域活動や家庭内での役割分担など、様々な方法がありますが、いずれも子供たちの成長に役立つものばかりです。
子供たちが他者と協力しながら問題を解決する力を身につけることは、将来の成功に繋がる大切なスキルとなります。
親としても、子供たちの成長を見守りながら、協働性を育む環境を整えていきたいですよね。
子供の協働性を育むためにおすすめしたいのはオンライン英会話!
オンライン英会話は、子供に異文化理解を促しながら協働性を育むためにおすすめしたい手段の一つです。
異なる文化背景を持つ先生や生徒と交流することで、子供たちは自然に他者と協力する価値のあるスキルを身につけます。
最近、我が家では子供が英語に興味を持ち始めたので、オンライン英会話を始めました。
最初は少し緊張していましたが、今では外国の先生や他の生徒と話すことが楽しいようです。
私の子供は少し消極的な性格ですが、コミュニケーションスキルが向上し、自信がついてきているようにも見えます。
子供が英語を学ぶだけでなく異文化交流を通して視野が広がり、よりオープンな考え方を持つようになってきたのは親としても、本当に良かったと感じています。
子どももオンライン英会話いいんじゃないかな、送迎なしだし、レッスン風景も見られるし、大体が25分で集中力ももちそう。
— あず ✴︎ (@Az7ssre) April 5, 2021
またオンラインでの学習は送迎の必要もなく柔軟なスケジュールで続けられるため、忙しい家庭にもおすすめです!
もし子供さんが興味を持つようであれば、ぜひ無料体験を活用してみましょう!
自分の子供に合ったプログラムかどうかを試してみるのもおすすめですよ。
実際の利用者の声をチェックして、あなたのお子さんにも最適かどうか確認してみてください。
協働性を高めるおすすめの習い事10選
協働性を育むためには、日常生活の中で様々な活動を通じてチームワークやコミュニケーションのスキルを身につけることが重要です。
特におすすめなのはオンライン英会話ですが、それ以外にも多くの効果的な習い事があります。
ここでは、協働性を高めるためにおすすめの習い事を10選ご紹介します。
① チームスポーツ
チームスポーツにはサッカー、バスケットボール、バレーボールなどがあります。
体力向上や技術の習得、仲間との絆が深まります。
- 協働性を高める理由:試合や練習を通じてチームメイトと協力しながら目標を達成する経験が得られる
- デメリット:ケガのリスクが伴う
子供の習い事としてチームスポーツはおすすめです!
— Kuroha | PdM (@booksoccermark) April 23, 2022
競技のルール、チームの決め事、暗黙の約束など守りつつ他人と協力してより良い成績を目指す中で子供の自制心をはじめとした非認知能力が育まれます。
ただし子供がそのスポーツやチームが好きじゃないなら非認知能力は伸びないのでそこは要注意。
② ボーイスカウト
ボーイスカウトは男女問わず参加でき、アウトドア活動やキャンプを中心とした団体活動を行います。
自然の中での活動を通じてサバイバルスキルやリーダーシップを養います。
- 協働性を高める理由:チームでの活動やミッションを遂行することで協力し合うことの重要性を学ぶ
- デメリット:屋外活動が多いため、天候に左右されることがある
8歳の息子はボーイスカウトに入っている。次回の持ち物は、隊長から子供に電話で伝えられ、伝えられた子供が次の子供に電話で伝える。
— 三浦-I 片吊り you- (@Vg1AOdXCpj5cxvT) February 12, 2025
息子は「手袋」を持参するように言われたので、その旨を次のメンバーに伝えた。すると、当日10人中2人が「寝袋」を持ってきて、1人は歯磨粉を持参したそうな。
このエピソードは、ボーイスカウトの活動の一環としてコミュニケーションの重要性を学ぶ良い例ですよね。
子供たちが情報を正確に伝え合うことの難しさと大切さを実感しながら、協力して問題を解決していく子供たちの成長も楽しみです!
ボーイスカウトでは、こうした経験を通じて協働性が自然に身についていくのですね。
③ ダンス
ダンスにはバレエ、ヒップホップ、ジャズダンスなど様々なジャンルがあります。
リズム感や身体の柔軟性を養いながら、体力も向上します。
- 協働性を高める理由:グループでの振り付けやパフォーマンスを通じてチームワークと協力の大切さを学ぶ
- デメリット:練習時間が長く、続けるためには根気が必要
④ キッズ英会話教室
キッズ英会話教室では、通学型の教室で外国人講師と英語を学びます。
英語力が向上し、異文化理解も深まります。
- 協働性を高める理由:クラスメイトとのコミュニケーションを通して協力する姿勢が自然と身につく
- デメリット:料金が高い場合があり、長期的な継続が必要
⑤ 科学実験教室
科学実験クラブでは、子供たちが科学の基礎知識を実験を通じて学びます。
実際の実験を行うことで、好奇心や探求心を育みます。
- 協働性を高める理由:複数人で一緒に実験を行うことで、協力することの大切さを学ぶ
- デメリット:実験材料や設備の費用がかかることがある
今日は息子が習い事の中でも一番楽しみにしている科学実験教室。
— みのり/N2023 (@minorin4) August 28, 2016
今日のテーマは「水の凄い力」
不思議に思う純粋な気持ちを大切にして欲しいと願い、通う事を決意。
実験中は子供たちの目がキラキラ✨本当に見てて可愛いし楽しいです‼️ pic.twitter.com/K4Lw9yQySF
お子さんが科学実験教室を楽しみにしている姿、素敵ですよね!
科学への興味を引き出し、協働性や探求心を育てる良い機会ですね。
⑥ 合唱団
合唱団では、複数の人が一緒に歌う団体活動を行います。
音楽の楽しさを共有しながら、発声やリズム感を養えます。
- 協働性を高める理由:声を合わせて一つの曲を完成させることで、団結力と協力の重要性を学ぶ
- デメリット:定期的な練習が必要で、発表会前は忙しくなることが多い
子供の頃の習い事のこと、ふっと思い出した。
— arnie (@kirkasvalo) March 14, 2024
合唱団に入ってて、駅まで歩いてバス代を浮かせて友達とジュースを飲みながら帰った事とか。それがすごく楽しかったんだよなぁ…
こちらの方は、合唱団の活動を通して友達と楽しい時間を過ごしながら、協力することの大切さを学んだようですね。
その経験が今でも心に残る思い出となっていることも素敵ですよね。
⑦ ピアノ教室
ピアノ教室では、楽器の演奏技術を学びます。
集中力や自己管理能力を養い、美しい音楽を奏でる喜びを感じることができます。
- 協働性を高める理由:グループレッスンや発表会を通して、他の生徒と協力する姿勢が自然と身につく
- デメリット:個人レッスンも多いため、協働性を高めるためにはグループ活動が重要
⑧ 料理教室
料理教室では、基本的な料理技術を学びます。
料理の楽しさを知り、食育にもつながります。
- 協働性を高める理由:複数人で一緒に料理を作ることで、協力することの大切さを学ぶ
- デメリット:材料費や道具の費用がかかる
子供に一つしか習い事させられないって縛りがあったらダントツで料理教室一択
— 池田P作 (@ikp1031) November 30, 2024
料理できるようになったら全てにおいて要領がよくなるし頭の回転めっちゃ早くなる
。料理できて損なんて絶対ないし料理上手いのに仕事や他のことは無能なんて人見たことない
料理教室は、単なる料理技術だけでなく、多方面にわたるスキルを育める習い事です。
協力することの大切さや計画性、問題解決能力も自然と身につくため、とてもおすすめです。
⑨ 書道
書道教室では、筆を使って美しい文字を書く練習をします。
集中力や忍耐力を養い、美的感覚も向上します。
団体競技としての「書道パフォーマンス」などでは、協働性や表現力を養う活動が含まれます。
- 協働性を高める理由:グループでの練習や発表会を通じて、協力の大切さを学ぶ
- デメリット:定期的な練習が必要で、初めての人には難しい
⑩ 美術教室
美術教室では、絵画や彫刻などの芸術活動を行います。
創造力や芸術的感性を養い、自分の表現力を高めます。
- 協働性を高める理由:グループで一緒に作品を作り上げることで、協働の精神が育まれる
- デメリット:材料費や道具の費用がかかることもある
特におすすめなのはオンライン英会話ですが、それ以外にも協働性を高めるおすすめの習い事10選をご紹介しました。
どの習い事も協働性やコミュニケーションスキルを育む素晴らしい機会です。
子供の興味や適性に応じて最適な選択を見つけ、楽しく充実した学びの時間を提供したいですね。
オンライン英会話が気になった方は、是非こちらの記事もチェックしてみてくださいね。
実際の利用者の声や効果について詳しく解説しています。
まとめ
この記事では、協働性とは何か・親ができること・そしておすすめの習い事についてなどを紹介しました。
協働性は将来の人間関係や社会生活において重要なスキルです。
親としても協働性を育むサポートをしていきたいですよね。
子供たちに協働性やコミュニケーションスキルを育む習い事は多くあり、特にオンライン英会話は異文化理解と協力の精神を育むのに最適です!
お子さんの興味や適性に応じた選択をし、楽しみながら協働性を育む経験を提供していきましょう。
これまで計10社以上のオンライン英会話を見てきた私がおすすめする『QQキッズ(QQEnglish)』の評判についてもぜひチェックしてみてください。
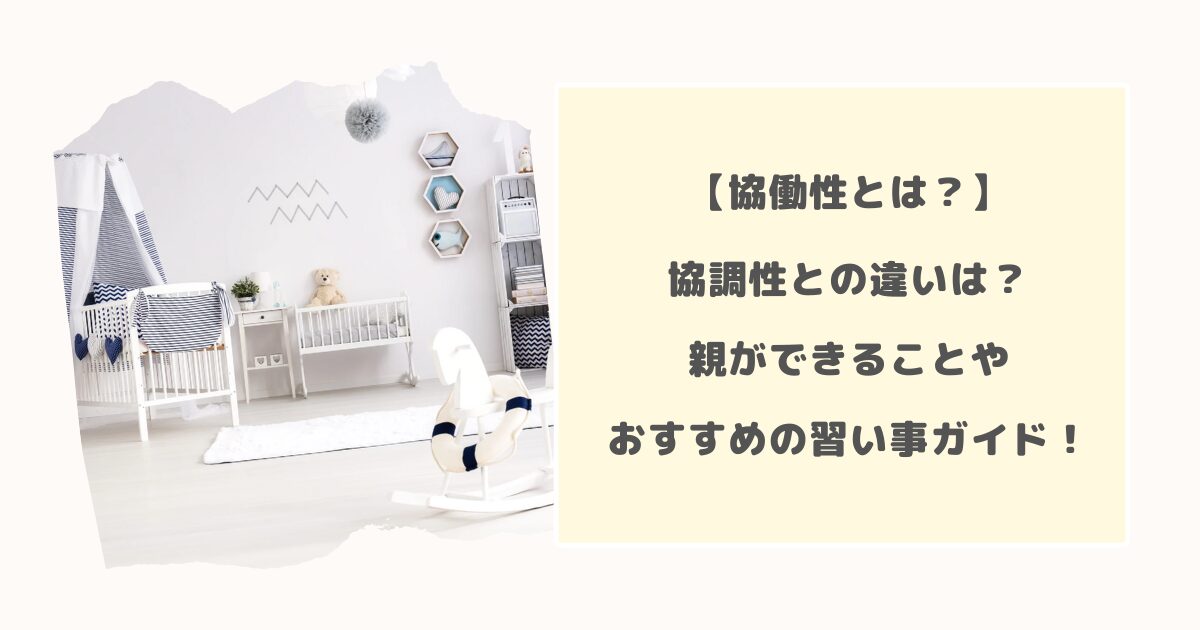


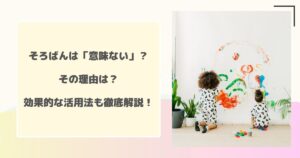
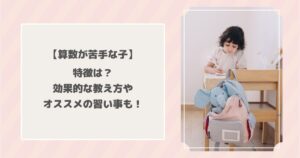



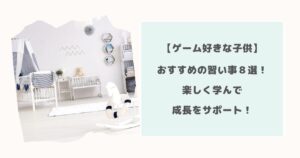
コメント